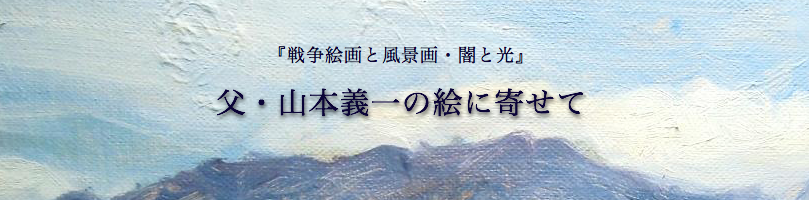『戦争絵画と風景画―闇と光』
十代から絵を描き始めた義一は美術学校進学を希望していたが、農家の四男ということもあり、学校には進学せずに独学で油絵を描き続けた。
1938年(昭和13年)3月、20歳で陸軍に入隊し、満州へ。3年後には太平洋戦争が勃発する。現地で大学夜間部3年に入学したが、4年生に進級する前に終戦になり、大学は閉学となり、現地除隊する。終戦の年1945年には帰国できずに満州にとどまり、2年間は引き揚げを待って暮らす。帰国前に「生活必需品株式会社」に入社しており、この会社発行の引き揚げ時の写真付き証明書が残っている。
満州での戦争経験については多くを語らなかったが、牡丹江の湖、鏡泊湖のほとりに滝があり、この地を浦島太郎が竜宮城だと思いこんだという、いわゆるご当地伝説を語ったことがある。実際、牡丹江にはナイアガラのような滝があり、戦地でなければ風光明媚な土地でもあったかもしれない。しかし、そんな観光気分とははるかに遠い現実があった。
当時、日本は満州国を建設し、大陸に進出しようとしていた。モンゴル人民共和国軍と満州国軍の国境線をめぐっての衝突をきっかけに、日本とソ連は1939年のノモンハン事件など国境紛争を起こす。日ソともに甚大な被害を出し、ソビエト連邦の勝利に終わったノモンハン事件に、義一も参加したという。終戦となり現地除隊したあとの2年間は、元日本兵であることを隠して生きのび、中国人にかくまってもらったことも、また同郷の日本人の民家で暮らし、生活のため豆腐を作って売り歩くなど苦労したようだ。
終戦から2年後の1947年に帰国。引揚船に乗り、福岡へ、そこから陸路で伊豆の一条までたどり着いたときの所持金は千円、リュックサックひとつでの帰還であった。
この引揚船を待つために牡丹江で行列する人々を描いたのが、百号の『噫、牡丹江よ!』である。戦争体験を描いた絵はこの一枚だけだ。青一色の色調のなかに、人々の群れが描かれている。夜明けを待つ人々を描いているのか、暗い海の底に沈んでいるような印象だ。
中央にぼんやりと浮かび上がっているのはベールで頭を覆った母とその胸に抱かれた子の姿、赤子に乳を含ませている母子像である。しかし、なにも食べていない母の乳は出ず、すでに息絶えているだろう赤ん坊の口に、それでも乳首を含ませているのだった。
ちょうどこの絵は2003年のイラク戦の頃に描いていたので、イスラムのベールをかぶった女たちを描いたものかと義一本人に聞いたところ、「牡丹江で引揚船を待つ人々の群れを描いた」と言っていた。そのときには絵の右上に文字は書かれていなかったと思う。
このブルーの濃淡のみの色彩で描かれた百号の大作は、それまでの写実的な風景画や人物画、静物画とは明らかに異なり、記憶のなかに深く沈殿していた戦争時の体験が、映像が、長い時間を経て発酵し熟成し、昇華された表現になっていると感じられるものだった。
戦争で失われた多くの人々、赤子も女たちもそして戦地で死んだ男たち、戦友たちの魂を慰撫するため、いや自らの魂をも浄化する鎮魂のための究極の1枚ではないだろうか。
義一はイラク戦争をおそらくテレビ放映で見て、なにかに刺激されたのかもしれない。長く記憶の奥にしまいこんでいた、しかし消そうにも消せない戦争体験を、終戦から実に58年たってはじめて絵画という手段によって表現できた。
人はつらいことやあまりに苦しいことを体験すると、そのことを忘れたい、思い出したくないと思う。戦争体験について取材させてもらった沖縄の人々の多くが語るのを躊躇して、それでもなにか伝えておかなくては、とようやく話してくれた。これは被災地の方々にもおそらく重なることだろう。被災者のカウンセリングにあたった専門家のインタビュー記事によれば、当事者が体験したことを「物語」として話すことができるようになれば、心の傷は少しずつ癒えていくという。
義一もまた、終戦から実に58年たって、ようやく戦争体験を絵画という「表現」によって描くことで、こころを癒すことができたのかもしれない。それは、それだけの長い時間を経なくては自らの戦争体験を客観視できないともいえるし、戦争というものが人間の心身に与える影響の大きさ、人生被害というものについてもまた考えさせられるものだった。
その後、この百号の絵には『噫、牡丹江よ!』と白い絵の具でタイトルが書かれていたのを見た記憶がある。サインはなかった。しかし、このあとこの大きな絵は枠から外されていた。 2014年11月5日、山本義一、他界。
2014年11月5日、山本義一、他界。
通夜の日、葬儀会場に絵を展示しようと思いつき、アトリエにしている部屋を探すと、カンバスがぐるぐるに巻かれてあったこの絵をみつけた。そのままの状態で、竹富島の風景画、湘南の風景画、伊豆の生家、二宮の自宅を描いた絵などとともに運び込んで飾ってもらい、あの世へおくりだすことができた。
満州に9年間滞在し、その青春期をほぼ戦争についやしたと言える人生は、この絵を画くことでひとつの浄化を経たように思う。
そして、沖縄竹富島の光と影をとらえた風景画は、戦争体験を暗(影)とすれば、桃源郷のような明(光)の世界として対極にあるものだ。
沖縄という唯一地上戦のあった土地へ行くことには複雑な思いもあったと思うが、竹富島滞在の3日間で義一は精力的に絵を描いている。
おそらくここで戦争という記号を押された沖縄ではないオキナワを見て、島人の暮らしに触れて、とても癒されたことだろう。
1月とはいえ日差しの強い戸外で、77歳が自転車の荷台にカンバス数枚と油絵の具を積んで絵を描くというのは、体力を消耗するものだ。フクギの樹の木陰で民宿の朝食の残りご飯で握ったおにぎりを広げるその姿を見て、室内に招じ入れ飲み物を提供してくれた島人のことを、義一はとても感謝していた。身なりをかまわない義一のいでたちは山下清のように見えただろうに、「てーどうん」の包容力と偏見をもたずに接してくれる態度に深く感銘を受けたのではないだろうか。以後、竹富島のテレビ放映があると、懐かしがって妻にそのときのことを語っていたという。
3日間の滞在を終え、帰る日の朝、民宿のお母さんに披露した絵は11点あった。
自宅周辺の『湘南の海のある風景』がふるさとの伊豆を連想させ、晩年の義一の心を癒したのと同じく、竹富島の風景は戦争で傷ついた心を慰撫したに違いない。島人の「まれびと」に対するやさしさ、それを感じたからこそ短い時間で多くの竹富島の絵を残したのではないだろうか。
2015年は戦後70年の節目の年。
多くの戦争体験者の方々が物故者となられている今、体験者の伝えたかったこと、戦争が個人の人生に与える影響とはどういうものなのか、絵を通して若い人たちにも感じてもらえればと思う。
世界のあちこちで、今も紛争が起こり、戦争が行われている――。
●沖縄県竹富島を描いた『竹富島の赤瓦屋根の集落と星砂の道』
●自宅のある神奈川県二宮周辺の『湘南の海のある風景』